はじめに:社会人が宅建に挑戦するのは無謀?
「資格を取りたいけど、仕事が忙しくて時間がない…」
「今さら宅建なんて無理かな…」
そんなふうに感じていませんか?
私は35歳を過ぎてから、仕事をしながら宅建士試験に独学で合格しました。
しかも、平日は朝と夜に少しずつ勉強するだけのスタイル。
正直、楽ではなかったけれど、正しい戦略と習慣があれば、社会人でも合格は可能です。
この記事では、特に「35歳以上で忙しい社会人」に向けて、
- 宅建の難易度と試験概要
- 独学でも合格できる理由
- 忙しい人向けの勉強スケジュールの立て方
- 時間の作り方と勉強習慣のコツ
- 実際に使った教材・勉強法
をお伝えします。
宅建士ってそもそもどんな資格?
まず前提として、「宅建士」は不動産業界で必要不可欠な国家資格です。
正式には「宅地建物取引士」といい、毎年30万人以上が受験する超人気資格。
宅建の概要
- 試験日:毎年10月頃(年1回)
- 合格率:約15〜17%前後(年による)
- 合格点:50問中35点前後が合格ライン
試験科目
- 宅建業法(20問)
- 法令上の制限(8問)
- 権利関係(14問)
- 税・その他(8問)
社会人におすすめな理由
- 独立・副業・転職の幅が広がる
- 難関すぎず、でも評価されやすい
- 資格手当がつく会社も多い
- 合格までの期間が半年〜10ヶ月で済む(短期集中型)
宅建は独学で受かる?結論:YES、ただし戦略次第!
私は独学で合格しましたが、ポイントは「教材と時間配分」にあります。
自己流に走りすぎると、時間もお金もムダになります。
独学でも大丈夫な理由
- 過去問ベースの試験なので「パターン学習」が有効
- 情報がネットや書籍で豊富
- 良質な市販教材がたくさんある
- 通信講座を補助的に使えばさらに安心
忙しい社会人向け|合格までのスケジュール例
「仕事も家庭もある中でどう勉強するの?」とよく聞かれます。
私のおすすめは、“1日1時間でも継続する”戦略です。
▶ 合格までのおすすめ期間:6〜8ヶ月(理想)
| 月数 | 目標 | 内容 |
| 1ヶ月目 | インプット中心 | テキストで全体把握&YouTube活用 |
| 2〜4ヶ月目 | 過去問演習 | 各分野の理解+アウトプット |
| 5〜6ヶ月目 | 模試&弱点補強 | 本番形式/時間感覚を養う |
| 試験直前 | 総復習&仕上げ | 苦手分野の重点対策/当日対策 |
社会人が時間を作るための工夫【私がやったこと】
忙しい人にとっては、時間の確保=最大の壁です。
でも、ちょっとした習慣の見直しで、毎日1時間は作れます。
✔ 時間の作り方アイデア
- 通勤中は「音声講義」で耳からインプット
- 朝30分早起きして1問でも解く
- スマホの通知をオフ/SNS断ち
- 昼休みの10分で1テーマだけ復習
- お風呂の時間にYouTube講義を見る
私の場合、平日:朝30分+夜30分、休日:2時間程度で回してました。
たったこれだけでも、半年で合格レベルに届きます。
独学で使った教材(おすすめ3選)
教材は本当に大事。自分に合うものを選ばないと、挫折の原因になります。
① みんなが欲しかった!宅建士の問題集 滝澤ななみ(TAC出版)
- 初心者でもわかりやすい構成
- フルカラー&図解が豊富
- 試験範囲を網羅していて安心
② 宅建士 出るとこ集中プログラム 吉野 哲慎
- 情報量を一般的なテキストの半分以下に圧縮して過去30年分の試験問題を分析している
- 法律用語をかみ砕いた解説で初学者でも読みやすく、理解しやすい文章で構成
- スキマ時間に学習しやすい構成で1テーマも短時間で効率的に学習
③ YouTube(おすすめ無料講義)
- 国際弁護士Tokyo Joeの宅建講座
- 宅建一発合格@れくお
合格する人・落ちる人の違いとは?
✔ 合格する人
→ 時間がなくても「毎日ちょっとずつ」やる人/繰り返し型の学習をしている人
✖ 落ちる人
→ 「週末にまとめてやる派」/完璧主義で進まないタイプ
結局、“どれだけ継続できるか”が勝負の分かれ目です。
まとめ:今からでも、宅建は間に合う!
宅建は「忙しい社会人でも独学で合格できる、数少ない国家資格」です。
あなたがもし、
- 今の仕事に不安を感じている
- 何かスキルを身につけたい
- 将来に備えて副業・転職の選択肢を広げたい
そんな気持ちがあるなら、宅建はその第一歩になります。
「忙しいから無理」ではなく、「忙しいからこそ、効率よく挑戦する」
それを、私はこのブログでずっと伝えていきたいと思っています。
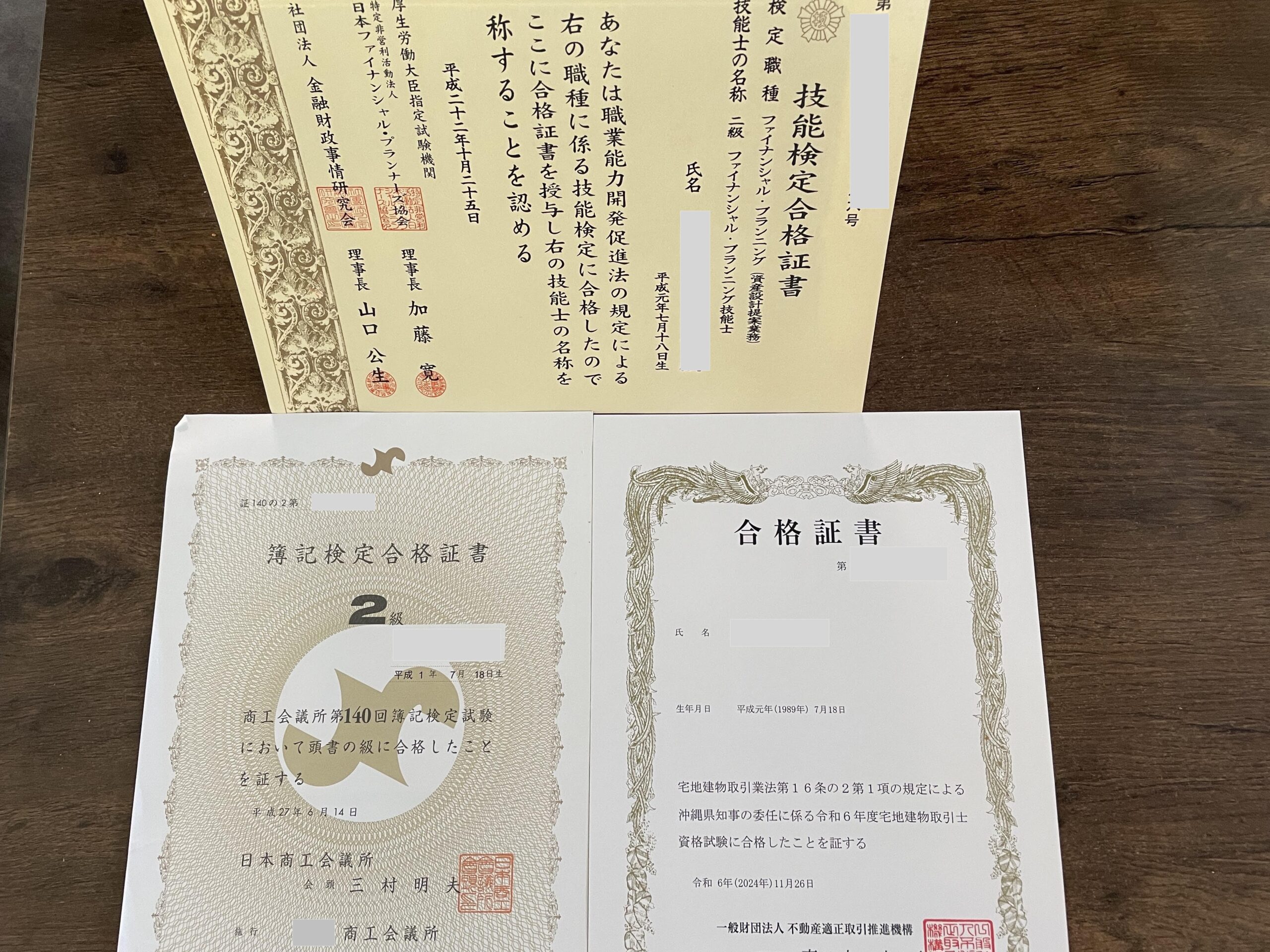

コメント